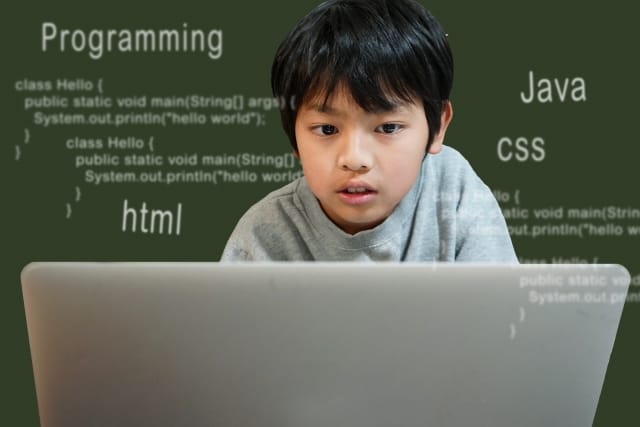情報リテラシー:親と子どものためのネット世界の羅針盤
2025.01.07

現代社会では、インターネットやSNSの普及により、
誰もが簡単に情報を発信し、受け取れる時代となりました
しかし、まだインターネットの世界は、35年です
急速な発展により、私たち自身が未だこのインターネットの世界に
追いついて行けていない現状があるのではないでしょうか
インターネットには、その膨大な情報の中には誤った内容や偏った意見も多く含まれています
誰でも発信できるよさがあり、マイナスがあります
そのため、情報を適切に選び、活用する能力「情報リテラシー」を身につけることが、
これからの世界を生きていく子どもたちにとって、
最も重要と言っても過言ではないと思います
本稿では、インターネットの重要性を踏まえ、
不登校の子どもを持つ親が、
子どもと共に情報リテラシーを育む方法を具体的に考えます
是非本コラムをご覧になり、あなたの子どもを護ってください
そして、これらかの世界を生き抜いていく力を育んでください
はじめに:情報リテラシーの重要性
情報を収集し、判断する力は、
現代の子どもたちにとって欠かせないスキルです
情報を収集することと、判断することは別です
「情報収集力はあるが、集めた情報を判断も評価もできない」
となると、どうにもならないのです
しかし、親がそのようなスキルを持っているとも限らず
親が子どもを教えると言うことに難しさがあります
言い換えると、親自身が自分の力で情報リテラシーを身につけていく
意識を持ってもらうことが大切です
総務省が示すように、情報の正確性や信頼性を見極めることは、
デマや誤った情報に惑わされず、
健全な社会生活を送るための基盤となります
「正にこれに尽きる」のではないでしょうか
特に、インターネットが当たり前のように存在する今、
情報リテラシーを欠くことで生じるリスクは計り知れません
例えば、SNSで拡散される「いじめ」や「ハラスメント」に関する情報は、
適切な判断力を持たないと簡単に信じてしまい、
被害者にも加害者にもなり得ます
また、誤った情報を拡散することで、
名誉毀損や人権侵害に関与してしまう恐れもあります
まだ人類はインターネットに
慣れていないとも言えるでしょうね
親として、子どもが正しい判断力を持ち、
情報を活用する力を育むためには何ができるのか
一緒に考えていきましょう
子どもの判断力を育てる具体的な方法:子どもと親との対話でつける
子どもの情報リテラシーを育むには、
ただ「気をつけなさい」と言うだけでは足りません
「何を気をつけるのか」
「何を学んでいけば良いのか」
「その方法は」
間違った学習を重ねると大変なことになってしまいます
学校でも教科は日々学習しますが、
このようなインターネットの情報に関わる
学習は、ほぼ無いといっても言いすぎではありません
日常生活で親がどのように具体的にサポートできるかを見ていきます
1. 情報の信頼性をチェックする習慣を教える
例えば、ニュース記事やSNSの投稿を見たとき、
次のような質問を投げかけてみましょう
「この情報はどこから来ているのかな?」
「日付はいつのものだろう?」
「他にも同じことを書いている情報はあるかな?」
これを親子で一緒に行うことで、そのままでは日々気づくことがないが
親の声かけによって子どもの気づきに繋がるでしょう
子どもは、情報の非常に大切な出所や信頼性を
自然と考える習慣を身につけます
特に、総務省が推奨する信頼できる
情報源(公式サイトや公的機関の発信)
を例として示すことで、
具体的な比較対象を与えることができます
2. 情報を比較する力を養う
子どもが
「Aというサイトにはこう書いてあったけど、Bは違うことを言っている」
と気づいたときがチャンスです
その際に、次のようなアプローチを行ってください
「どちらの情報がより専門家の意見に近いと思う?」
「具体的なデータが載っている方はどっちかな?」
※専門家の信頼度も重要です
信じ込まないようにしてください
例えば、SNSで見た健康情報について
「総務省の資料や医療機関の公式サイトと比べてみよう」と提案することで、
より信頼性の高い情報を選ぶ能力が育ちます
※総務省のホームページ、厚生労働省ホームページ等について
一定の信頼性は、ある程度エビデンスにより担保していると考えてもよい
3. 実際に検索する方法を一緒に練習する
上記にあったように、「~しなさい」という声かけでは、
「算数の勉強しなさい」と同じで
具体性に欠けるため、子どもも戸惑ってしまいます
子どもに「調べてみなさい」とだけ言うのではなく、
一緒に検索の仕方を練習することが最も大切です
・検索キーワードを工夫する方法を教える(例:「いじめ 対策 文部科学省」など)
・上位に表示される情報が必ずしも正しいとは限らないことを伝える
・複数の情報を比較する大切さを説明する
このように親が実践を通じて教えることで、
子どもはインターネットをただ使うだけではなく、
活用する力を身につけます
インターネットは、活用力が何より大切な力と言えます
もちろんですよね
ネット活用の現状と問題点:親子で乗り越えるしかない

1. ネットの利点
インターネットの有用性は、いうまでもありません
昔で言う、「三種の神器」ではなく
「一種の神器」とも言っていいものです
今や人類になくてはならないものです
インターネットは膨大な知識の宝庫です
教育用プラットフォームやオンライン教材を活用すれば、
学校に通わなくても学びを深めることもできます
用途に応じて何でもできるのです
スタディサプリやKhan Academyは、
基礎学力を強化するのに最適です
YouTubeでは、科学実験やDIYプロジェクトなど、
興味を広げる動画が豊富に揃っています
オンライン学習アプリを通じて、も
子どもの興味に合った分野を学ぶことも可能です
これらのツールを活用することで、
子どもは学ぶ楽しさを感じることができます
親としてこれらのツールを一緒に探索し、
どのように使えば効果的かを考える時間を持つことを考えてください
これらは一例です
インターネットの世界は、無限大に広がる世界です
親子で学んでください
2. ネットのマイナス面
一方で、ネットには次のようなリスクも潜んでいます
ネットは怖いもの
これは、一面では誰でも理解している側面です
下手をすると「命に関わること」も考えられますよね
正に、「諸刃の剣」です
では、「インターネットは使わない」とはならないのです
誤った情報の拡散: SNSでのデマは、時に社会問題へと発展します
過剰な依存: 長時間の利用により、生活リズムが崩れる可能性があります
いじめやハラスメント: SNSを通じた攻撃的な発言や晒し行為は、深刻な心理的影響を及ぼします
これらのリスクを避けるためには、ネットの利用時間を親子で管理し、
SNSでのコミュニケーションにも目を向けることが重要です
特に、親がルールやマナーを子どもと一緒に考え、
話し合うことで、
ネットを安全に使う基礎を築くことができます
ネットリテラシーは、親、大人と子どもで作っていくもの
と、言えます
なので、子どもの問題ではなく、親の問題ではない
二人の問題として考えてください
親がすべき具体的な支援:ほったらかしでは無理
1. ルールを設定する
ネット利用に関するルールを親子で話し合い、
具体的に決めましょうということですが
これは、昔から言われていることです
正にいたちごっこ
例えば、以下
・利用時間を決める(例:「夜9時以降はスマホを使わない」)
・投稿前に親と内容を確認するルールを設ける
・誹謗中傷や差別的な言葉を使わないといったSNSマナーを徹底する
大切なことですが、痛い目に遭って気づくことにもなります
しかしルールは必要、無くてはないものです
社会に存在するすべてのことに、「ルールは存在する」と
言えますよね?
何かルールのないもの、決まっていないものがない
そういうものはないのではありませんか?
いかがですか?
学校でも同じです
ルールが必要であれば、子どもたちと話し合って
ルールの存在を肯定します
「楽しく生活するためには必要だよね」と、、、
ルールは単に押し付けるのではなく、
なぜそのルールが必要なのかを丁寧に説明することで、
子どもの理解を深めてください
親の腕の見せ所です
2. ネットのポジティブな使い方を示す
・興味のあるテーマを一緒に調べてみる
・教育系アプリを活用して学びを深める
・地域活動や趣味のコミュニティをオンラインで探す
例えば、旅行や歴史に興味がある子どもには、
Google Earthを使って
仮想旅行(楽しいですよ、親子で旅してみませんか?)
を提案したり、
歴史ドキュメンタリーを一緒に観たりすることで、
ネットの良い使い方を示ますよね
トライしてみてくださいね
3. トラブルが起きたときの対処法を教える
これが重要です
私も娘に尋ねられました
「どうしよう」と、本当に抜け出せない恐怖に襲われることもありますよね
誰でも一度は経験したことがありますよね
万が一、誤った情報を信じてしまったり、
いじめに遭遇した場合、次の手順を示してください
冷静になる: すぐに反応しない
※ほったらかす、相手にしないことも対応のひとつです
大人に相談する: 親や学校の先生に状況を伝える
※黙って悩むことは最悪、失敗は当たり前、言いづらいこともありますが、
誰でもあります
前もって何でもいいから伝えるように言っておきましょう
咎めることもしません
ほったらかしておくと実態は悪化する場合があります
証拠を保存する: スクリーンショットを撮るなどして記録を残す
これらを具体的に教えることで、
子どもはネット上のトラブルに対しても冷静に対応できるようになります
情報リテラシーを育むための親子の取り組み:もう一度おさらい
1. 定期的な対話を持つ
ネットだけど、アナログなんですよね
人間の世界は、
情報リテラシーを育むためには、
親子で定期的に話し合う時間を設けることが大切です
というか、親子でネットを使うことです
最近見た情報について感想を述べ合うだけでも、
子どもが情報を批判的に考えるきっかけになります
ネットだけではありません
「批判的な思考:クリテイカルシンキング」
どうも批判というと、相手に対する悪口を言うと捉えられがちですよね
日本の良くないところです
外国では、当たり前のことです
批判的思考とは
「前提となる事実を明らかにしながら、多角的考えること」
です
批判とは
「良いところ、悪いところをはっきり見分け、評価・判定すること」
どうですか?
大切なことでしょう?
子どもには
「批判的な思考」を身につけさせる、まずは、
「そうかな?」と考えてみる習慣をつけて欲しいです
疑ってみましょう、何事もです
2.日常生活の中で情報リテラシーを実践する
買い物をする際に商品レビューを一緒に確認したり、
ニュースを一緒に分析するなど、
日常生活の中で情報リテラシーを実践する場面を増やしてください
何でも練習です
縄跳びでも跳んでみないことにはどうにもなりません
子どもに実践させてください
させないと免疫力と対処法が分からなくなってしまいますよね
3. 成功体験を積ませる
子どもが正しい情報を選び、
それをもとに行動した結果がうまくいったとき、
必ず褒めてあげましょう
やはりここでもアナログ
褒めてあげることです
すると楽しくなりますよね、子どもは、
この成功体験が、子どもにとっての自信となり、
情報リテラシーをさらに向上させる原動力となります
ここまで来ると、どうのようにネットと接していけば良いか、
子どもはイメージできるようになっています
怖さはあっても、楽しみの方が強くなりますよね
ネットに振り回されるのではなく、ネットを乗りこなす
そんな子どもに育っていきますよ
楽しみです
まとめ:だからアナログなんだよ
さて、最後に、このコラムを締めくくりましょう
子どもたちにとって情報リテラシーは、
これからの社会を生き抜くための基本的な力です
そして、最大限生かされなければならない、重要な力です
この、基本から重要までは、非常に大きな空間があります
子どもがネットの世界を、
自由に安全に羽ばたいていけるようにしたいです
このコラムでは、親子で情報リテラシーを育む方法について考え、
日常生活で実践できる具体的な取り組みを伝えてきました
まだまだ十分であるとは思っていません
情報リテラシーを育むためには、
親が子どもの模範となることが重要です
この模範というのは、ネット等の情報を熟知していると言うことではありません
あなたが、「ネットは苦手だよ」でもいいのです
子どもと一緒にネットに向かう姿勢です
そのことで、子どもとのネットにおける信頼関係ができます
その上で
情報の信頼性を一緒にチェックする習慣を作ることから始め、
ネットの利点とリスクを具体的に教え、
ルールとマナーを明確にすることです
また、親子で検索の仕方を練習し、
信頼性の高い情報を見極める方法を共有することも有益です
やっぱりここでも「アナログ」ですよね
さらに、ネット利用に関するルールを親子で話し合います
この段階になると、子どももネットに対する理解とルールの存在の必要性も
「納得の気持ち」になっていると思います
トラブルが起きた際の対応方法を具体的に教えることが不可欠と述べてきました
自動車の運転で言うと、ブレーキです
ブレーキの効かない自動車は安心して乗れません
そして、トラブルを相談できる関係ですよね
情報リテラシーは、単に誤った情報を避けるためだけではなく、
正しい情報を活用して自分の可能性を広げるためのスキルです
でなければ意味が無い
不登校の子どもたちやその親にとって、
情報リテラシーは新しい可能性や将来を切り開く鍵となります
このコラムが、親子で情報リテラシーを学び、
より安全で豊かなネットライフを送るためのきっかけとなることを願っています
情報の海で迷わないために、
今日から始められる小さな一歩を踏み出してみてください
羅針盤は、旅を始めてこそ役に立ちます
未来を切り開く力は、子どもたちの手の中にあります
キーワードは
「アナログ」

メンタルオフィスKaze代表の視点
本当にこれ「情報リテラシー」は重要ですよね
世の中、世界的に、重要度が増すばかりです
「間違った情報を信じ込んで、自分の行動に影響を及ぼしていく」
これは本当に危険なことです
しかしこのように情報に私たちは常に晒されているのです
だからといって、インターネットを介した情報から逃げる
怖いからと言って避けてしまうのでは、今の時代は生きていけません
何でもそうです
使い方によっては便利であるし、使い方を間違えば危険である
命すら失う場合があることは、今も昔も同じです
刃物は、下手をすると危険です、しかし、包丁やナイフを使わずに
料理ができない
児童車は交通事故を招くが、乗らないという選択肢は難しい
いかに安全に使うかということですよね
情報⇒刃物、情報⇒自動車
情報は避けるものではなく、うまく使っていくものです
おもにインターネットから得る情報をどう使っていくか
これからの世の中は、大きな課題です
しかも、インターネットの世は、過去30年程度の時代です
インターネットの無い時代でも情報は非常に大きな価値を持つものでした
インターネットの時代になってより高度に情報の活が高まったと言えます
情報の中にはダイヤがあります
いかにダイヤをつかむか、玉石混淆です
しかも、価値のないもの間違ったものは掴んではいけません
「価値あるものを掴む」
間違った情報に影響されると大変です
大人でも難しいことを、これから子どもに身につけて貰おうというのが
「情報リテラシー」です
みんなが持っていない答えに迫って行くには、冷静に論理的に考えていくしかありません
課題は、流れてきた情報、自分が得た情報、自分が探した情報が正しいかどうか、どう判別するのか
そして、情報を信じ込まず、「自分は間違っているかも知れないという」冷静さを持って判断すること
間違うと大けがをすることすらあることを理解する
自分だけではなく、他人を傷つけてしまうこともある
YouTube等で見た内容を信じ込まないこと、、、
考えただけでも難しいことではないですか?
動画を何回も見ると、そうだと思い込んでいくことも想像に難くない
これらから子どもが流されずに自分の思いや考えを持つ
自分の「思いや考えである」と「他人から思わされる」ことにならないようにすること、
過剰に影響を受けないように、なっていくこと、
非常に重要ですよね
情報リテラシーで重要なことは、判断基準を確立することです
ファクトチェックが正しくできることです
ファクトチェックとは、
(Fact-checking)
世の中に広まっている情報や言説が、事実に基づいている稼働かを検証する活動のことです
インターネットやSNSで真偽不明な情報(フェイクニュースやデマ)が瞬く間に拡散する現在において
非常に重要になっています
ファクトチェックを適切に確実に行うこと、行う意識を持つことが最も重要です
その手順を述べます
1.対象となる言説の特定
検証すべき社会的に影響の大きい言説を選びます
(政治家の発言、SNSで拡散された情報などから)
2.事実・証拠の調査
公的機関の発表、資料、複数の信頼できる情報源などを用いて、
徹底的に事実関係を調査します
この徹底的にが重要です、これは、安易ではないという意味です
3.検証結果の発表
調査結果に基づき、言説の真意を判定します
この時に、なぜその判定に至ったか、根拠となる情報を明示します
判定するときに、
・事実
発言が真実に基づいていること
・誤り
発言が事実に反していること
・ミスリード
一部の事実は含まれているが、意図的に文脈がゆがめられ、誤った解釈に導かれていること
・根拠不明
発言の真偽を確かめるための十分な証拠がないこと
ここまで日ごろ瞬時にファクトチェックができるかどうかは分かりません
しかし、現在は「エビデンス」は大切、と
このことは社会的に認知されています
情報も同じであると言うことです
子どもには、この「ファクトチェック」の習慣をぜひつけてください
簡単に安易に信じることや拡散することは危険です
必ず真偽を「調べる」こと、
信頼できる情報源や人物を、ある程度日ごろの言動から見つけておいて
信頼できる人の発言を聞いてみること、
とにかく慎重になるべきです
これからは、情報が大きな影響力を持つ、
非常に価値を持つ時代へと更に加速していくことが予想できます
不登校問題でも同様にどこでどのように情報を得るか
他の情報も、間違いのない情報をどのように得ていくのか
「情報リテラシー」が非常に大きな影響力を有する時代になると考えます
恐れていてはいけません
情報を豊かに活用して、取捨選択し未来への羅針盤としていきましょう

サロン概要
アクセス
- 所在地
和歌山県御坊市 - 電車でお越しの場合
御坊駅下車 - 営業時間
平日9:00~17:00 / 土日祝定休
090-9621-7137
ご来社の場合はお電話でお問い合わせください