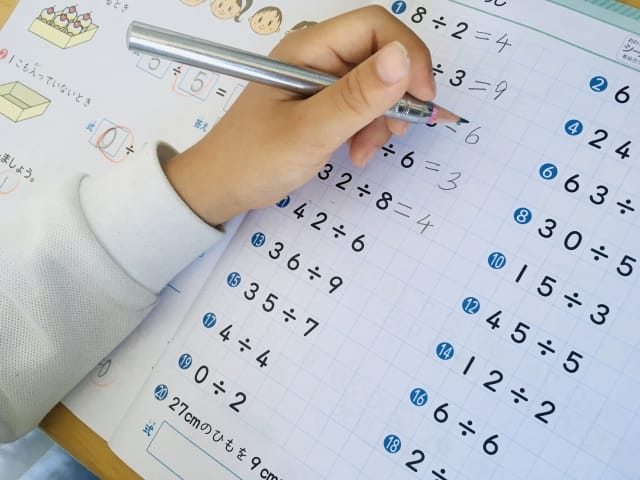おすすめのコラム
先生という大人とどう関わっていくか
先生の人柄によって、
仕事への理解や子どもへの理解によって
「不登校」に影響すると言わざるを得ません
不登校の原因として「先生との関係」は挙げられます
このコラムでは、先生との関係ついて考えてみたいと思います
「不登校と家庭環境~親としてできること~」
不登校がここまで増えてきた原因が「家庭」にあるとするなら、非常に単純な問題になります
しかし、そうでしょうか?
「家庭環境は要因のひとつ」と捉えることで、
絡み合った様々な子どもへの影響を解きほぐしていく「解決の力」になります
「不登校と家庭環境~親としてできること~」について、書いていきたいと思います
学校には多くの課題や問題があります
それらのほとんどの問題を解決できる
魔法のような手段は、、、あります
それは
「授業づくり」です
良い授業づくりによって、子どもの関係は良くなり、
子どもが生き生きと学習に望むようになるのです
今回は、良い授業づくりと子どもの生活について述べていきます
甘やかされて育った人と一緒に仕事をするのって、迷惑?職場の環境は悪化する!!

ここでは、「甘やかされて育った人」が、どんな人に育ち、職場でどんな振る舞いをし、周りにいるあなたにどんな影響を与えるのかを話題にしていきたいと考えます
甘やかされて育てられると、困ったことになる、職場に居る人の特徴を考えてみて、子育てが原因と仮定して
このコラムでは、その影響を考えていきます
インターネットやSNSは私たちの日常生活に欠かせない存在となっています
早い段階からデジタル技術に触れる機会が増えています
インターネットやSNSの利用が、子どもの発達や健康に与える影響については、慎重に議論する必要があります
本稿では、インターネット・SNSの利用が子どもに与える影響について、
ポジティブな側面とネガティブな側面を中心に解説します
職場で”気になる人”とは?甘やかされた子どもが大人になった?子育ての影響!
あなたの周りの人との人間関係の中、職場の後輩、先輩、上司(同僚)、
友達との関係などで“気になる人”がいるのではないかと思います
この人はどんな子育てを受けてきたのか気になりませんか?
このコラムは、周りの大人の中で“気になる人”がどんな成長をしてきたのか、あなたの子育てに関わってお話しします
情報リテラシーが子どもの未来を創る:子どもたちと親が知るべき、今の時代の「情報リテラシー」
今、全国的に、あるいは、地域的に、情報が私たちの生活を大きく揺るがしてしまう状況です
情報リテラシー及びネットリテラシーの存在が非常の大きくなっていることに鑑み、
現状からこのコラムが不登校、子ども、保護者も留まらず社会全体に早急に必要であると判断しました
私のコラムが、すべての人を守る一助となることを願って投稿します
甘やかせて育てると、将来職場で気になる人になる
あなたの職場で、
「この人、ちょっと気になるよね」
「どんな育てられ方をしたのだろう」
と、思いながら自分の子育てを考えます
「この人は、甘やかされて育ったのでは」
「私も子どもを甘やかせている」
「子どもがわがままだ」
甘やかされて育った人の将来、
職場での様子についてです
気になることがあれば、参考にしてください
【子どものいじめ・学校の実態】親が気になる対処法:知らなければ動けない、失敗をしないために必要なこと
今回は、一般的な話を避け、
学校で長年勤務した来た経験から
「いじめ問題」の取り組みや
学校の実態について
お話ししたいと思います
ネットリテラシーが未来を創る:子どもたちと親が知るべき「情報リテラシー」の重要性
親として子どもを守り、ネットリテラシーを身につけさせることは、将来の彼らの成功を支える基盤となります
インターネットに触れずにこれから生きていくことはできません
親として子どもを守り、ネットリテラシーを身につけさせることは、
将来の彼らの成功を支える基盤となります
これらについてのコラムです
読んでみてくださいね
不登校でも心配しないで!小学4年生の学習と将来への指針
不登校は特別なことではありません
まず、あなた自身が「不登校は悪いことではない」と受け入れることが大切です
そして、子どもの未来を長い目で見守りながら、
適切な対応を取ることで状況は必ず改善します
「甘やかしすぎではないか」
という心配や、
「もっと厳しく対応すべきなのでは」
という思いが頭をよぎることが少なくありません
このバランスをどのように取ればよいのか、
不登校の親子が直面する重要なテーマです
子どもが学校に行きたくない:勉強が原因、休むとさらに勉強が遅れてしまう!親の心配
子どもは、勉強が将来の自分のためであることを知っているのです
子どもによっては、プレッシャーを感じてしまうのです
子どもがどのように「勉強」と関わっていくか、
不登校の原因になるケースも含めて考えていきます
「ひきこもり」はどうなってしまうのか、現状は?
「ひきこもりになってしまうのでは」
このことが、親にとって一番心配なことではないでしょうか
見えない将来をどのように見ていくのかが最も大切です
今回のコラムでは、ひきこもりをどのように捉えていくのかについて考えていきます
子どもが学校に進んで行くとき
ランドセルを背負って友だちと元気よく登校する子ども、
見ていてこちらがうれしい気持ちになります
「いつもそんな子どもたちを見ていたい」
そう思うのです
あなたも思うでしょう、そんな気持ちでしょう?
そのためには、学校はもちろんのこと、
家庭や様々な環境がやること、大切ですよね
「子どもが進んで学校に行く気持ち」について、
大切なことを考えていきます
不登校の子どもの悩み(気持ち)
不登校の子どもたちが抱える悩みや気持ちは、多様で深刻なものが多く、
その背景には様々な要因が絡んでいます
彼らの気持ちや悩みを理解し、適切に対応することは、
彼らの成長と未来にとって非常に重要です
不登校の子どもたちが感じる可能性のある主な悩みや気持ちについて詳しく考えてみます
何のために学校に行くの?あなたの答えは!【子どもたちにとっての学びの意味】
学校に通うことの意義や目的はどこにあるのでしょうか?
本記事では、子どもたちにとっての学校教育の重要性や、学校に通うことがなぜ大切なのかを考察すると同時に、必ずしも学校ではない、学びの多様性について考えます
親が考える学校に行く理由:【不登校と子どもの成長】

子どもが小学校へ入学すると、親も初めての経験から、喜びや期待は大きくなります
子どもが学校に行くことは、決して親の願いを実現するためではありません
本記事では、不登校を経験する子どもを持つ親の立場から、
学校に通うことの意義と、不登校との向き合い方について考察します
甘やかされ型男子と不登校:【親の育児とその影響】
男の子に対しては、親の愛情が過度に表れることがあり、その結果として甘やかされ型育児が行われることが少なくありません
本記事では、甘やかされ型育児と不登校、男の子に対する親の愛情について考察します
甘やかされ型と発達障害:共通点と相違点、支援の在り方
「甘やかされ型」と「発達障害」
という二つの概念は、
しばしば混同されることがありますが、それぞれ異なる背景と特徴を持っています
この記事では、甘やかされ型と発達障害の共通点と相違点を探り、
適切な支援の在り方について考察します
親の過保護や過干渉は、子どもの成長に深刻な影響を及ぼします
育てられ方の背景には、親の強い愛情と期待があります
本記事では、甘やかされて育った子どもの特徴、親の思い、そして健全な子育てのためのアプローチについて探っていきます
甘やかされて育った人と不登校の関係:社会性、仕事、人間関係の影響
甘やかされて育った人が一定の特質を表す背景には、
親の過保護や過干渉が大きく関与しています
このような育て方が、子どもの社会性、仕事、
人間関係にどのような影響を与えるのかについて考察します

甘やかされて育った子どもは、自立心や自己管理能力が欠如し、
対人関係のスキルも未熟であることが多いとされています
本コラムでは、甘やかされて育った人の特徴、その原因と影響、そして対策について詳しく探ります
甘やかされて育った人の社会的要因と不登校
甘やかす行為が子育ての場面で、常態化することが問題なのです
現代社会では、甘やかされて育った子どもが増えていることが指摘されています
親の過保護や甘やかしは子供の成長に深刻な影響を及ぼし、
その結果として不登校などの問題が生じることがあります
注目されるのが「甘やかされ型」の過保護が原因となるケースです
子どもは生まれたときから家庭環境に影響を受けて育ちます
家庭にいる大人(親)は、そんな関わりを子ども持っていくのか、子育ても仕方はどうか、
子どもの特質はどうか、与える影響は非常に大きいと、、、、
年々不登校は増え続け、地方自治体の人口にも迫るのではないか、という子どもたちが不登校に陥っているのです
不登校は日本社会において深刻な問題です
今回は、特に「甘やかされ型過保護」が原因となるケースを扱う
「甘やかされ型過保護」が子どもに影響があることは容易にイメージが湧きます
この気持ちが吹っ切れないでいる
親としては当然です
学校に、他の子どもたちと同じように
元気で通ってほしい
これがすべての親の願いですよね
不登校に陥る原因は?
家庭環境や育て方が原因とされるケースも増えています
これは、親として大変気になるのではないでしょうか
自分の家庭の環境に問題がある、あるいは、
自分が子どもに精一杯関わってきた関わり方、子育てが原因になっている
もしそうなら、どのように改善していったらよいのでしょうか
つらいものですよね
あなたの気持ちが一番凝縮した瞬間でしょう
不安な毎日が続いていきます
まずあなたの気持ちは、
「どうしたらいいの!」
ですね
これから
どんどん不登校が進んでいったらどうしよう?・・・
あなたの抱えた問題を推察するのは、とても難しい事です。
パズルのように必ず当てはまるようなピースはないからです。
でも、パズルのピースを探すことはできます。
あなたに当てはまるピースは必ず、あります。
検索結果、、、
ほとんどの人の気持ちの中で、「学校は行くもの」なのです
「学校に行かないという選択肢はない」
このことについて…
子どもにとって友達の存在は大きい、
影響力のある存在であることは
いうまでもありません
我が子にとって、「友達」とは、どのような存在なのか
きっと今まで深く考えてきたことは、ないのではないでしょうか…
「遊び」
子どもが、こう言って自分の行為を「はぐらかす」こと
学校の教師をしているとよくあります
このような場合、あなたならどう答えますか?
気になりますよね?
してはいけないのではないか
言ってはいけないのではないか
気を使いますよね?
我が子ながら…
あなたは誰かに話をしたい、
聞いてもらいたいと思ったことはありますか?
その誰かとは?
不登校児童生徒は、毎年増えて行くばかりです
どうしてこう、多くの子どもたちが学校から足を向けてしまうのでしょう
「子どもが弱い」「親や家庭の育て方が悪い」のでしょうか?
このことについての話したいと思います
このように増え続けている原因には、
多くの要因があるでしょう
どのように考えても、
「ある家庭の、ある家庭による、ある家庭の問題」
不登校とは、何なのか
不登校とは、どうして起きるのか
不登校とは、どんな状況を指すのか
不登校とは、ある子どもの特有のことなのか
不登校とは、どんな対応をするべきなのか
不登校とは、関わる団体や集団が何をすべきなのか
不登校とは、これからも増え続けていくのもなのか
不登校とは、何とかできないものなのか
「甘やかす」とは、どういう状態なのか?
不登校になった子は、「甘やかされて育った子」
が、陥りやすいの?
学校に行けない
勉強が遅れる
友だちと疎遠になる
毎日家にいるため生活習慣が乱れる
家庭環境が変化する
気をつけることとは?
| オフィス名 | メンタルオフィスKaze |
| 代表者 | 奥 明浩 |
| 住 所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 ※時間外も対応可能 |
| 定休日 | 不定休 |
| TEL | 090-9621-7137 |
| メール | 1z2b3m4w1234@gmail.com |
| 事業内容 | 心理カウンセリング |
| 保有資格 | 学校教員1種免許状 メンタル心理ヘルスカウンセラー メンタル心理インストラクター 福祉心理カウンセラー 福祉心理アドバイザー チャイルド心理カウンセラー コーチングプロフェッショナル |
| URL | メンタルオフィスKaze | (officekaze.com) |