
情報リテラシーは、子どもが将来この世界で生き抜いて行くために、
欠かすことができない、非常に大切なスキルです
もう一度、リテラシーの意味を確認します
リテラシーliteracyとは、
「特定の分野に関する知識や理解力、それを活用する能力」
のことです
この力、情報リテラシーを私たち大人は、
子どもたちに最も力を傾けて、
身につけさせる努力をすることが大切です
とは言っても、どのようにリテラシ-を、
特に情報に関するリテラシ-を身につけさせたらよいのか、
迷いますよね
難しいですよね
でも、あなたにしてほしいのです
このコラムでは、情報リテラシーに注目して
子どもに対してあなたにしてほしいことを、
お話ししていくので、是非お付き合いください
情報リテラシーとは何か
現代の社会では、インターネットに関わって様々な問題や犯罪が
起きていることはご存じの通りです
インターネットの中にある多くの情報は、正しいのか信じて良いのか不明です
あなたは、インターネット内の情報を、どのように扱っていますか?
また、集めた情報の信憑性はいかがですか?
あなたも、いろんな場面でインターネットを活用していると思います
例えば、
美味しいランチのお店を探したい
様々な必需品を購入したい
ショッピングをしたい
今度家族で遊びに行きたいが、どんなところがよいか
難しい言葉や知りたいことを調べたい
何か出来事があったが、詳しく知りたい
Aという人が話題に上っているがどんな人だろう
仕事上の調べ物をしたい
など様々だと思います
インターネットの情報、とても便利ですよね
もう無くてはならないものです
インターネットは様々なシーンで役に立っています
しかし、どうでしょう
お店にしろ、品物にしろ、書籍にしろ
その中にレビューがありますよね
レビューをあなたは信じますか?
少し本当かなと考えてみますよね
☆がいくつあるのかも気になりますが、
その都度、どうかなと思いますよね
お客様にレビューを依頼して、
お返しに商品券を出すということが実際にあります
とにかく、このようなことから
あなたはネットに全幅の信頼を置いているわけではありません
では、その信憑性(信頼性)をいかに高めていくのか
それが正にリテラシーに繋がっていくのです
もう一度、、、
「信憑性を高める行動をとる」「とれる」
「そして、本当に信用できるであろう情報を得る」
そしてようやくたどり着くのです
加えて、情報リテラシーとは、
「情報の収集、理解、活用、発信の能力」
これです
では、やっていきましょう
情報は基本的に「怪しい」という気持ちを持つことが大切
私たちは、信じる気持ちが正しくて、怪しいという気持ちを持つことは、
あまり誠実ではない、というような気持ちをどこかで持っています
あなたはどうでしょうか?
基本的に、
その気持ちは、間違ってはいません
しかし、これが「危険です」と言わざるを得ません
信じてしまうところに、正しい証拠があるかどうかです
話は逸れますが、
よく、だまされてお金を取られたというニュースを目にしますよね
なぜだまされたんだろうと思いますよね
あり得ないとも思いますよね
実際にそういった詐欺に遭っておられる方がいらっしゃいます
インターネットの中の情報が詐欺であるとまでは言いません
しかし、多かれ少なかれ、信じるという同じ構造の失敗があるように思います
相手を信用すること、
相手はだまそうとしているかは別にして、
発信者がどういう人であるかは、私たちには分かりません
そこでどのように対応すれば良かったのか、です
リアルの世界、アナログの世界でも、
このインターネットの世界でも
同じなのです
まずは、飛び込んできた情報を信じ込むことがないように、
常に冷静であることです
情報は巧妙であるかも知れません
幾重にもこちらが誤解を生むように仕組んだものであるかもしれません
間違いの無い判断をしていくのです
判断については、以下で述べていきます
とにかくこの項では、「情報を鵜呑みにしない、疑ってみる目を持つ」です

子どものスマートフォンとSNSの問題と依存症
子どもの携帯電話が問題になって久しいです
学校でもしきりに、保護者向けの学習会に講師を呼んで実施してきました
あなたも一度は参加したことがあるのではないかと思います
インターネットがこの世に現れて約30年、
ガラケーを使うようになって約25年になるのでしょうか
ガラケーの時代が終わりを迎えつつ、スマホの時代に突入してきたのが
2000年から2010年までの間です
スマホの時代になり、さらに問題が複雑化してきました
私は苦手だからとおっしゃる人もいると思いますが
実際、インターネット時代の約30年を生きてきているはずです
あなたの理解がこれからの子どもたちの情報リテラシ-に影響をもたらします
さて、保護者向けの学習会を学校が開催しているように、
親子でこのネット時代を乗り越えていくことが必須です
そこで、「気をつけなさい」「あまりスマホばかりやらないように!」
など、注意することでは、子どもとスマホの心配を回避することはできません
アナログな子ども関係では、実際に見えますから、ある程度安心感があります
しかし、スマホの中で起きている問題があるとするならば、見えないところで
起きている問題となってきます
心配ですよね
少し話を間に挟むと、
「アナログの世界でも、インターネットの世界でも、子どもに影響を及ぼすのは同じです」
よって、どちらも同様に子どもへの影響がありますから、
様子をしっかり見ておくと、
子どもに何か問題があるのかを推し測ることができます
話を戻します
SNSは、人と人とのつながりを全国に、全世界に広げることが可能です
多くの人とつながり、友達を増やし、自らの可能性も広げるのです
SNSは人とのつながり、アナログと同様に、トラブルも発生します
これはご存じですよね
子どもにできるかどうかは別にして、
フェイスブック、XTwitter、インスタグラム、YouTube、TikTokなど
様々在りますが、よく使っているのはラインでしょうか
ラインも個別のやり取りだけでなく、ライングループもあります
様々なサイトには危険も存在します
多くの友達とのやり取りでは、
すぐに返事を返さなければなら脅迫か観念脅迫か観念があります
ラインでは既読が付く付かないなど、
お互いに疑心暗鬼を生むこともあります
これはあなたも経験がありますよね
とにかく時間も必要です
勉強に時間を費やしてほしいところに、
SNSに時間を取られたり、
動画サイトに時間を取られたりするなど
ついついスマホが気になって集中できないことや、
集中力も切れていくことにもなります
外国(オーストラリアなど)では、
15歳まで自分のスマホを持たせないように決めています
子どもにとって多くの問題をはらんでいるスマホ、
考えれば考えるほど心配になっていきます
「ルールを決めて守らせる」か、
かつてのテレビゲームのように「取り上げる」か、
考えられますが、現実的には不可能でしょう
「ルールを決めまもらせる」ことができるといいのですが、
個々の子ども、親子関係などによっても違ってきます
問題は、もっと簡単にできること
「親の管理下に置けるのかどうか」です
これが大切です
親の管理下に置かなければダメです
親の管理下というのは、親が力ずくでルールを決め、
守らなければスマホを取り上げることではありません
これでは子どもとの関係性を含めて正常ではありません
悪化します
スマホの利用料金は親が払いますよね
ギガなども契約によりますよね
そんなところでもコントロールが可能です
イメージの中に、どれだけ子どもとスマホを置けるのか
これが、
「親の管理下」です
誤情報、デマの拡散、フェイクについて
「怪しい情報」について、もう少し話します
まず「誤情報」は、怪しいどころか誤った情報ですよね
このような誤った情報が流れてきた、
あるいは、検索した場合にはどうするのか、
災害などの場合は、命に関わります
この誤った情報に影響されると大変です
そして、この誤った情報を拡散すると
「デマの拡散」になります
一人や二人、仲間内だけであれば影響も少ないでしょう
このコラムは、インターネットがテーマです
今の世の中では、山を越え谷を越え、広く流布されてしまいます
根拠のないデマの拡散は、今、社会問題になっています
そういったことに荷担しないために、
「誤情報をつかまない」、
「デマを拡散しない」ことが重要であることは
いうまでもありません
荷担すると大変なことになります
フェイクニュースももちろんです
正しい情報をいかに得るかが今必要です
これは以下の項で引き続き書きます

誹謗中傷・人権侵害・個人情報漏洩などに関わってしまうことが簡単に起きます
情報リテラシーの最大の課題と言っても
言いすぎではありません
特に知らない間に問題に荷担してしまう
危険性すらはらんでいます
後から問題となり大変なことになってしまうことが、無いとは言えません
【誹謗中傷】
命に関わる問題です
言葉の暴力です
実際に口から発する場合もあれば、
SNS内で発信する場合もあります
いずれも誹謗中傷に変わりはありません
例えば学校で、
友達に対して悪口の落書きをする
手紙のような形式で悪口を書く
これも誹謗中傷ですよね
他の人がやっているから、
同じような発信だから、これは通用しません
みんな同じ犯罪です
SNS等に書き込む場合は、
相手を傷つけるような発信ではないことに細心の注意が必要です
本当のことだからいい、そういうわけではありません
仮に本当のことでも、誹謗です
誹謗中傷の意味を確認しておきます
誹謗「相手の悪口を言う」
中傷「根拠のない嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること」
誹謗中傷とは、
「根拠のない悪口やデマを言いふらして他人の名誉や人格を傷つけたり、
社会的評価を低下させ足りする行為
であり言葉の暴力です
インターネット上で特定の個人を対象に投稿されることで、
内容によっては名誉毀損罪や侮辱題などの刑事責任を問われる可能性があります」
インターネット上では、集団意識と自分の匿名性により、発信のハードルが下がることに、
特に心しておくことです
【人権侵害】
人権は何人も侵すことない個人固有の権利です
他人の人権を自分の人権同様に大切にする気持ちは持たなければなりません
当然ですよね
【個人情報漏洩】
身近な問題として、個人情報の漏洩は意識しておく必要があります
自らの個人情報も漏洩させるのは危険です
しかしながら、自分が自分の個人情報をネット等に挙げるのは、
個人の責任です
ご商売など、自分の仕事に関して必要な情報を発信することは必要なことです
発信者が、誰の情報をどんな目的で発信するかが問題になります
商売でも仕事でもなければ不用意に情報を挙げることは控えることです
自分以外の他人の情報は、写真、名前など、個人を特定する情報です
以下、確認しておきます
個人情報とは
「生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などによって特定の個人を識別させる情報」
を指します
次に挙げるもの、
「電話番号、アカウントID、メールアドレス、免許証、マイナンバーカード、DNA、指紋、サービスの利用、商品の購入、パスポート、顔写真、人種、信条、社会的身分、健康診断の結果」など、
これを見ると個人情報はかなり広い意味になりますよね
個人情報漏洩は犯罪であると理解して気をつけてくださいね

正しい情報を「収集し活用する力」が現代社会では必須です
「正しい情報を集める意識」を持つことが何より大切です
ぱっと見つけた情報に飛びつかないことです
とは言え「正しい情報」を集めることは難しい事です
なぜか?
それは、得た情報が「正しい情報」かどうか分からないからです
「正しい情報を集める意識」をもって、
得た情報が「正しい情報」かどうかを
判断していくことができる、
このスキルを磨くことが必要になります
情報を収集、比較評価していくためには、情報が1つではダメです
多くの情報を収集するしかありません
まずは、「収集力」ですね
いくつぐらいがいいでしょうか
「適切でいくつかの種類の情報」
いくつとは言えませんが、
集めながら比較評価も加えていくことが必要ですね
その同時進行の中で、収斂していくことです
「最終的にこうかな?」と思える状態になっていくことです
収斂させることで、収集比較評価のスキルを上げることです
繰り返し正しい情報を得る練習をすることです
あなた(母親)といっしょに、収斂させていく練習を行ってください
会話の中で、「これは正しいのかな?」「こんな情報もあるよ」
「どちらの情報が正しいのかな?」「もう少し関係のある情報を集めてみようね」
「情報の出所はどこからかな」「もっともらしい出所だからと言っても正しいとは限らないね」
親子で対話しながら情報収集の収斂のさせ方を学ばせるのです
具体的でなければ行けません
そして、情報が正しいのでは無いかという段階に来たときに、
それでも情報が正しいと信じ込まないようにしながら、
次は「活用です」
集めた情報を活用して、レポートを書くのか、SNS等で発信するのか
発信する方法により、
ようやく世に出すことも可能になるのです
しかし、情報の出所はきちんと示せるようにしてください
相手(他者)を傷つけてしまうことに気をつけて、
しっかりとネットを活用してくださいね
まとめ
情報リテラシーを子どもに身につけさせて、
「ネットから子どもを守る」
では、
守るだけでいいの?
難しいところですが、それじゃいけない!
のです
広い意味では「子どもを守る」ことに繋がるのかも知れません
子どもたちが様々な事件に巻き込まれている報道もあります
いじめの問題もありますよね
事件に心を痛めることが多いです
親としては心配ですよね
守る意識だけでは、インターネットやスマホに触れさせないで行こう
という消極的な考え方にもなっていきます
反対に、小さいときから、むしろ情報に触れさせていくことです
免疫を付けて行くことだけではなく、
いかにすれば予防ができ危険を察知し回避しながら、
安全にインターネットの波に乗っていけるかです
上述したように、外国では15歳まで子どもに
個人のスマホを持たさないことを決めました
国レベルで決めることがいいのかどうかの言及は避けますが、
早い段階での情報リテラシー教育が、いきなり15歳で始めるのではなく
一歩先に進むことが大切ではないかと思うのです
あなたと子どもで情報リテラシーを育てるのです
家庭の努力だけでは、もちろん十分ではありません
学校を含めた教育によって身につけさせるのです
パソコン教室があり、タブレットがあり、プログラミング教育があります
しかしこれらは、インターネットを使うということです
例えると、自動車の運転は教えるが、危険性や法律、
モラル、ルールなどが抜けているというようなことです
自動車の運転だけでは、危険でしかありません
このコラムで話してきたのは、インターネットやスマホの仕組み、使い方ではありません
インターネットやスマホという自動車を、
どのように安全で、自他共に命を守り、
楽しく豊かなドライブにしていくのかといういことです
「運転は子どもに任せても大丈夫だね」
こんな情報リテラシーを子どもにつけたいのです
子どもがインターネットという現代の素晴らしい技術を活用して、
様々な危険を回避し、自らの力で豊かな未来つくっていけるように、
あなたと私たちは、応援していかなければいけないですね
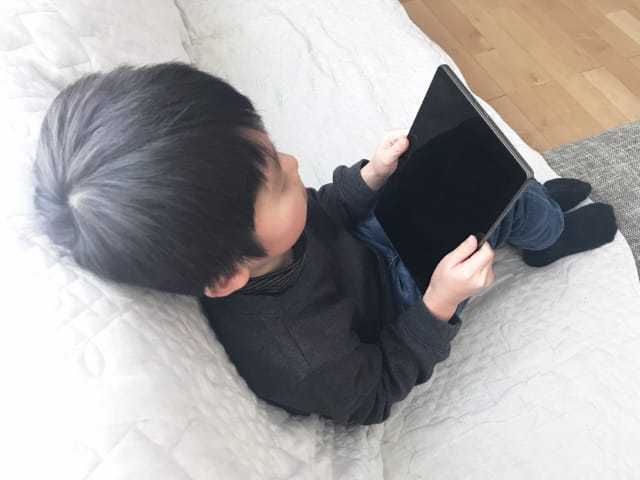
メンタルオフィスKaze代表の視点
今、世の中で起きている様々な問題、政治面から社会面、
ネットを外して論じることはできません
それだけネット社会の中で私たちが生きていて、
翻弄されていると言っても過言ではありません
インターネットが世に出てきたのは、
アメリカでは1960年後半、日本では1980年後半
一般企業や個人が利用できるようになったのは、1990年中盤、
この1995年頃にWindows95が発売され、
インターネット接続機能がOSに搭載され個人利用が容易になり
一般家庭への普及が本格的になりました
携帯スマホについては、
1990年前半は、まだポケベルの時代
1999年にiモードなどの携帯インターネットサービスが開始され
2008年頃にiPhoneが発売、Androidスマホも登場しました
この歴史を見ると、2000年以降にインターネットサービス
が活発になったと言えるのではないでしょうか
SNSの様々な問題が今、噴出していますが、高々四半世紀の経過でしかありません
そんな高速な発展に私たちがついていくことができていないのは明かです
たくさんのデマや中傷、様々な策略が蠢いているのではないかという疑心暗鬼に陥る人々
大変な時代を迎えました
以前から子どもに及ぼすインターネットの影響は問題になってきました
スマートフォンの使い方やルール
現在の子どもたちの様子を見れば、常にスマートフォンを手にしています
大人、親は心配ですよね
しかし、このインターネットは、これほど「諸刃の剣」を言い表したものも珍しいと思います
インターネット、本当に便利ですよね
無くてはならないものの中にインターネットを挙げる人は多いでしょう
勉強や調べ物、仕事環境の変化、人とのつながり、
挙げたらキリが無い必要日可決なものとなりました
世の中に他にも危険と隣り合わせのものもあるでしょう
正しく使うことですよね
みんな分かっていることです
正しく使うためには、知識が必要です
ルールも必要です
様々な習慣や身体、健康、私たちのすべてに影響が及びます
スマートフォンの規制にまで動いている国もあるほどです
子どもたちが、
そんなつもりではなくても人を傷つけてしまうことも十分考えられます
間違った情報に影響されてしまうことも危険です
こうなるとインターネットは非常に危険な道具にもなります
しかし、もう現代社会では無くてはならないものになっています
避けて通ることも不可能です
親が子どもに危険だからと遠ざけておくとどうでしょう
将来、インターネットをうまく乗りこなすことができるようになるのでしょうか
お年寄りは、インターネットが怖いとおっしゃいます
これは反面正しいことですが、怖いからと言って逃げていては
自分の生活に非常に役に立つ情報を得ることはできません
「知らないから怖い」とも言えるのではないでしょうか
子どもには、私は、「教育で乗り越えさせる」ことが重要であると思います
インターネットから逃げない、スマートフォンから逃げない
そこで、情報リテラシーの重要度が非常に増していきます
あんまりどっぷり浸かっていると脳の成長の面も気になるし、
セロトニンの分泌なども気になりますね
生活習慣も気になりますね
依存症ももちろん気になります
しかし、情報を扱うという意味において、
様々な情報が正しいかどうか判断する力を
身につけさせたいです
現在社会には情報が溢れています
個人が情報と適切に向き合い、活用するために必要なのは総合的な能力です
【情報リテラシシーを構成する4つの能力】
1.情報収集・検索能力
2.情報の評価・判断能力
3.情報の活用・分析能力
4.情報の作成・発信能力
インターネットやSNSの普及により、誰もが容易に情報発信・受信できるようになりました
そこで問題が、
【フェイクニュース、デマ、誹謗中傷、個人情報の漏洩】
これらはリスクです
これらをしっかりと理解し、
「ファクトチェック」
を行える力、
「社会に広まっている言説や情報が客観的な事実に正確に基づいているかを検証し、
その結果を公に発表・共有できる」
・対象の言説の特定
・証拠(エビデンス)の調査
・真実性の判定
・結果の発表、共有
を心がける
【心得】
①情報源を確認する
誰がいつどこで発信された情報か確認する
②報道されている情報が、オリジナルの文章やデータの一部を切り取ったものでないか、
可能な限り確認する
③複数のソースでクロスチェックする
一つの情報だけではなく、複数の信頼できる情報源で同じ内容が報じられているかを確認する
④「事実」と「意見」を区別する
その情報が客観的な事実なのか、それとも個人的な意見や推測なのか明確に分けて捉える
これら心得を踏まえつつ、
適切に判断すること、
その適切の中には、「事実だから言ってもよい・発信しても良い」とはならないので、
発信することは、相手がいること、相手がどう感じるか、
自分の身に置き換えて考え、人と人とのつながりを大切にすることは、
ネットを活用する社会においても大変重要であることを、
子どもたちには教えていきたい、
理解してもらいたいと思います
私たちが相手にしているのは、生身の人間なんですね
インターネットの社会は、今や避けて通ることができない社会です
より豊かに活用できるように、道具は使うものであることを理解して
子どもたちには、より良い社会の中で安全に
豊かに生きていってほしいです
メンタルオフィスKaze

サロン概要
| 名称 | メンタルオフィスKaze |
| 英文社名 | mentalofficekaze |
| 代表 | 奥 明浩 |
| 所在地 | 和歌山県御坊市 |
| TEL | 090-9621-7137 |
| メール | 1z2b3m4w1234@gmail.com |
アクセス
- 所在地
和歌山県御坊市 - 電車でお越しの場合
御坊駅下車 - 営業時間
平日9:00~17:00 / 土日祝定休

