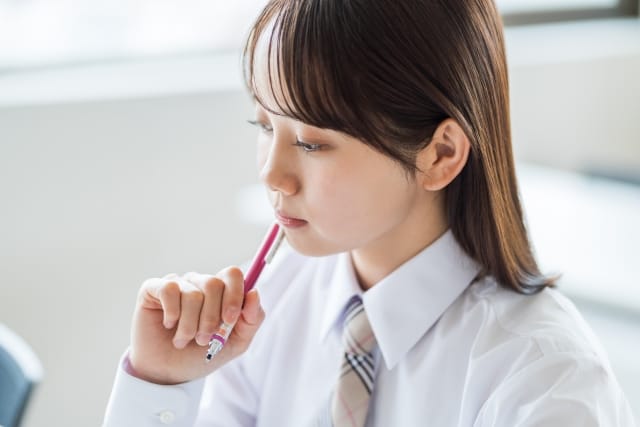高2女子Sさんのケース(母親と娘の関係)
2025.05.11
現状・家庭
ある日の火曜日、午後の昼休み、
事務所に電話が入った
高校2年生、娘の母親である
母親が言うのには、昨日から娘が
「学校に行かない」といって休んでいる、
どうしたらよいのか困っているとのことであった
父母と娘三人(妹二人、本人長女)の家庭だ
娘が自らの意思で二日間休んでいて、
家で寝ているということであった
元々友達が少なく、高校一年生の時に連れていた友達二人と
クラス替えによって分かれてしまったとのことであった
中学校ではバレーボール部、高校では文化部に入っていた
情報
1回目の電話では、できる限り多くの情報を得る必要がある
話を聞くことで、母親の話したいという思いと情報を得ることの
両方を満足させるために、
母親は、小中学校から友達が少なく関係づくりが苦手である
勉強は普通より少しできる子である
姉妹との関係もよい
親子の関係もよいということであった
高2になって、弁当は一人で食べることが多いのだという
子どもの情報は、母親からしか得ることはできない、が
相談をしたい、話をしたいという思いを持っているのは、母親である
相談者は子どもではなく、母親である
まずは、母親の悩みや思いを聞き取っていく
情報が十分ではないが、話を聞きながら一定の方向に進める努力をしていく
まとめ
誰もがそうだが、「どうすればよいか」
分からない、それが正直なところである
学校はどうだろうか?
この女子生徒の学校に行きたくない、学校に足が進まない気持ちを
どこまで理解しているだろうか
一般的に、人間は、環境におかれ生活していくと、疲弊していくものである
少しずつエネルギーがなくなっていくのだ
1か月か何週間か、少しずつ疲れてきたのは容易に理解できる
「独りでいる感覚」であったのかもしれない
母親に話をしたのは、
まずは、学校に連絡を取り様子を伝えること、
担任に状況を伝え理解してもらうこと、
これは、「学校で何かあったのか?」
というような立場ではなく、
「知らせること」に必要性である
知ることで、担任や学校は目を配るようになる
知らなければ何もできない
特に中学校以上は、担任といえども教科担任制である
朝と帰りのホームルーム、教科の授業でしか、教室には来ない
そして、
大切なことは、
『これから連絡を取り合うことができる関係をつくっておくことである』
このことを母親に話した
この母親とは、この後数回話をすることになる
その間に、経過は良好で大きく休むこともなく回復していった
母と娘の親子関係について(メンタルオフィスKaze代表の視点)
ジェンダーの問題は、人権問題ではなく
親と子どもの関係で性別に関して影響はあると考えられます
母と娘は当然女性同士です
父親よりも身体的な面では話はしやすいのですが、
同性であるが故に難しい面も時には出てきます
娘が母親を女性としてみてしまうと
反発も生まれてくることも考えられます
父親と娘の関係よりも、人生において最も深く複雑な絆があります
多くの母娘の関係では、感情を共有できる深い共感があります
娘は、母親から多くのことを学び人生に大きな影響を与えます
思春期や青年期には自立を求める娘と、
保護したい母親の間で葛藤が生じます
衝突が起きることもあります
同性としてみてしまうところに、
微妙な感情が生まれます
母親と娘の間に、時代とともに変化する社会や価値観により
感覚的なギャップも生じることがあります
母と娘は深くつながり、人生においても困難も喜びも、
支えとなりながら人生を歩んでいくことができます
娘が不登校になった、不登校傾向に陥ったときに、
母親は、心配のあまり精神的に不安定になってしまう場合もあります
言いたいことを言わないで辛抱することもストレスになるでしょう
「オープンなコミュニケーション」を心がけて、
自分の感情や考えを冷静に率直に伝え、娘の意見にも耳を傾けることが大切です
高校2年生ともなれば、娘は精神的に大人です
娘の人格や選択を尊重し、独立した個人として認め対応することが望まれます
不登校であっても適切な距離感を保つことが大切です
お互いのプライバシーの尊重も健全な関係の維持には重要です
母と娘の関係は、人それぞれですが、
人生のパートナーとして、
一生付き合っていける太い絆があります
あなたは心配しないで、
娘を信じて関わっていってください

御坊市、地域の状況を含めて考える
御坊市には、高校が3校あります
日高高校、紀央館高校、和歌山高専です
生徒数2025年
日高高校「男子287名、女子353名」
紀央館高校「男子235名、女子292名」
和歌山高専「男子690名、女子196名」
このように多くの生徒が学んでいます
以前からの問題で、中途退学がありました
通っている生徒の地域は、御坊市だけではなく
日高郡内が対象になります
みなべ町では、田辺市方面の高校に進学する生徒もいます
和歌山高専の通学は、バス、バイクなど
日高高校は、自転車、JR⇔紀州鉄道など
紀央館高校は、自転車、JRなど
広域にわたって通学しています
中には、近畿大学附属高等学校、智弁和歌山高校に進学している生徒もいます
日高高校は、中高一貫教育を行っています
多くの地域の子どもたちが、これらの高等学校に進学しています
御坊市の小中学校の子どもたちにプラスして、
各市町の子どもたちが集まって来ています
子どもたちの登下校の様子で、年々増え続けてきたのが
「保護者による送迎」です
特に雨天等天気の悪い日は、送迎の車でごった返すようになりました
それほど広い道ではありません
一般の車両も行き来するため更に混雑し危険ですらありました
これらの対策として、学校は送迎をできるだけ控えてくれるように訴えたが
ほとんど効き目がありませんでした
今では送迎当たり前になっています
現在も地域の学校近くの道路を見てみても、午後3時ごろの下校時には
子どもを乗せて発車していく車が群れになっています
道路はもちろん停駐車禁止区間の標識が上がってます、
学校には校区があり、一定の範囲で通う学校が決められています
上記学校の校区が非常に広域であり、
子どもの足で何十分もかかるような範囲ではありません
この学校であれば、ほとんどの場合約20分程度歩けば家に到着するだろうと考えられます
もちろん迎えも様々なケースがあり、そのまま病院や塾等に送るといったことも考えられますが
日常的に見られることはありません
これらの様子は、紀央館高校の前でも見られていて、
高校生でも保護者の送迎があります
では、この送迎に見られる保護者・親の意識の変化ですが
かつては、歩いて学校に通う、通わせることに対して「当たり前」と考えられたのではないでしょうか
いつからこのような意識になったのか、、、
もう結構昔です、20年くらいでしょうか
親たちも送迎を受けてきたのか、それとも送迎を受けていないが
自らの子どもには、車での送迎をしているのか、
様々な事件や交通事故のニュースから危険を感じて心配なのか、
しかし「歩いて送迎する保護者はいない」のです
ここで、車での送迎について賛否を問題にしているのではなく、
保護者・親の子どもへに意識の変化です
外に現れている様子で、この車での送迎は、
保護者・親の子どもへの意識、子育ての変化が
表れているのではないかと考えられます
この「甘やかし」ともとれる保護者・親の意識は、ここでは
一般的な地域の実態として、
ひとつのケースとして置いておきたいと考えます
さて、高校2年生のSさんのケースのように、
友達関係が発端になっているように感じるケースについて、
本当に友達関係が問題なのでしょうか?
友達づきあいがそれほど得意ではなく、
一定の仲の良い友達と過ごすことが多い子ども、
友達関係が苦手な子ども、
大人になっても人付き合いが苦手な人、
そう感じる人はいますよね?
友達関係が問題で学校に行きたくないという
友達が学級にいなくなったというこのケース、
友達がいないことに耐えられない子どもの責任なのかということです
違いますよね
子どもは自分の置かれた環境、大人によってつくられた環境を
自らの力で改善していくことはできません
子どもの中には、何とか耐えて順応しようとする子どももいるでしょう
しかし、このケースのように耐えられなくなるケースもあります
不登校問題は、子ども個人の問題ではないことがよく分かるケースです
「子どもの弱さ」を問う意見もあるでしょう
しかし、子どもが育つ環境、子どもが学習できる環境をつくるのは
親であり学校です
不登校問題は、環境の問題、環境は子どもがつくったものではない、
子どもの居場所や学習及び成長の場をつくるのは、親や学校など周りの仕事であると、
このことを踏まえて取り組んでいきたいものです
メンタルオフィスKaze

サロン概要
アクセス
- 所在地
和歌山県御坊市 - 電車でお越しの場合
御坊駅下車 - 営業時間
平日9:00~17:00 / 土日祝定休
090-9621-7137
ご来社の場合はお電話でお問い合わせくださ