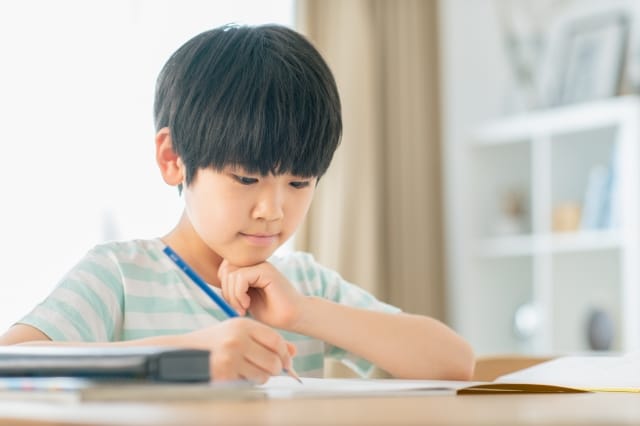不登校を乗り越える【勉強への対応】
2024.12.07

はじめに
不登校児童の勉強は、その特性や状況に応じて柔軟な対応が必要です
不登校の背景にはいじめ、家庭環境の問題、学業のプレッシャー、
精神的な不安などさまざまな要因が絡んでいます
そのため、画一的な教育方法ではなく、
個々のニーズに合った学びの環境を提供することが求められます
本稿では、不登校児童が直面する学習の課題、現在利用可能な支援、
効果的な勉強方法について解説します
不登校児童が抱える学習課題
学習の遅れ 学校に通えないことで、授業内容を継続的に学ぶことが難しくなります
特に、積み上げ型の学習が求められる算数や理科、
語学では、基礎が不足すると後の学習にも大きな影響を及ぼします
モチベーションの低下
不登校の児童は、学校への嫌悪感や自己否定感を抱え、
学習に対する意欲が低下しやすいです
また、「自分だけが取り残されている」という焦りが、
さらにモチベーションを奪う原因になります
孤立感とサポート不足
学校外での学びを支える環境が整っていない場合、
児童は孤立しがちです
学びのペースを調整しながら、
適切にサポートする仕組みが必要です
心の健康と学業の両立
精神的な不安やストレスを抱える児童にとって、
無理に学習を進めることは逆効果となる場合があります
心のケアと学習支援をバランスよく行うことが求められます
不登校児童を支える学習環境
不登校児童を支援するためのさまざまな取り組みが行われています
フリースクールと適応指導教室
フリースクールや適応指導教室(教育支援センター)は、
子どもたちが安心して学べる環境を用意します
これらの施設では、個別の学習計画や、
少人数での活動を通じて児童の自尊心を育みます
オンライン教育
最近では、インターネットを活用した学びが広がっています
自宅で動画授業を受けたり、オンラインの家庭教師を利用することで、
学校に通わなくても学習を続けることが可能です
学校との連携
学校が提供する個別支援計画(IEP: Individualized Education Plan)
を活用することで、学習内容を調整したり、
段階的な登校を支援する体制が整備されています
家庭学習のサポート
親が学習の進行を見守ることも重要です
教材や学習アプリを活用しながら、
無理のない範囲で学習を進めることができます
不登校児童の勉強方法とポイント
1. 学習目標の設定
児童の状態に合わせて短期的・具体的な目標を設定します
例: 「1日10分だけ国語を読む」「好きな教科だけを学ぶ」
2. 興味を活かした学習
子どもの好きな分野や興味のあるトピックを学びの入り口にします
ゲームや漫画、趣味などを活用して、学びへのハードルを下げます
3. 反復と習慣化
学習は少しずつで構いませんが、継続が重要です
毎日同じ時間に簡単なタスクを設定することで、学習の習慣を育てます
4. 成功体験の積み重ね
子どもが「できた」と感じられる体験を積み重ねることが重要です
褒めるポイントを増やし、自己肯定感を高めます
5. 柔軟なスケジュール
朝が苦手な子どもには昼から学習を始めるなど、
児童のリズムに合わせたスケジュールを組むことが効果的です
6. ソーシャルスキルの向上
不登校児童にとって、学業だけでなく社会性の回復も重要です
オンラインやフリースクールで同年代の仲間と交流できる場を提供します
保護者と周囲の役割
1. 子どもの心を理解する
不登校の背景には、学校や友人関係への不安やストレスがあります
まずは子どもの話をしっかり聞き、安心できる環境を作ることが大切です
2. 過度なプレッシャーを避ける
学び直しのペースを押し付けると、かえって子どもの負担になります
焦らず、小さな一歩を応援する姿勢が必要です
3. 専門家の力を借りる
カウンセラーや教育相談機関を利用し、子どもの学習と心のケアをサポートします
特に、親が対応に迷ったときには、第三者の視点が役立ちます
4. 学校や地域との連携
学校との定期的な情報共有や、地域の支援制度の活用を検討します
多くの自治体で不登校支援プログラムが整備されています
まとめ
不登校児童の勉強を支えるためには、
個々の状況に合わせた柔軟な対応が求められます
学習の遅れやモチベーションの低下といった課題を克服するためには、
フリースクールやオンライン教育といった多様な選択肢を活用することが重要です
また、保護者や学校、地域社会が一体となって子どもの成長を支えることが、
長期的な成功につながります
子ども一人ひとりが持つ可能性を信じ、
その個性やペースを尊重した学びを提供することで、
不登校という状況を乗り越える力が育まれるでしょう
メンタルオフィスKaze代表の視点
不登校で困ることとは?と聞かれると
1番は勉強と答えるのではないでしょうか?
勉強が遅れると、学校の戻るときにも取り戻すことが大変です
将来大人のなったときに、勉強の遅れ、
学校に行っていないことへの不安でいっぱいになりますよね
しかしこれは、勉強を乗り越えていくときに、
まずは、「学校に行こう」というのが頭にあります
課題が第二段階になっていて、
1,学校に行く
2,勉強をする
「1が成り立たなければ2は成り立たない」
ということです
これでは、学校に行くことができなければ、1番の問題である勉強
心配になる勉強にはたどり着くことはできないということになります
オーストラリアの砂漠の中で住んでいる子どもは、
ラジオを使って毎日学習すると聞きます
学校に行くことができないからです
今の時代、東京にいても北海道にいても、沖縄でもどこでも
Wi-Fiの完備しているところでは、仕事は可能です
そんな時代になっています
学校に行かなければ勉強ができない昔ではないのです
昔でもどうでしょう?
みんなが学校に行けたかどうかは分かりません
現在の状況で課題を解決できる方法を考えましょう
学校に行くこと取り組みは必要ないと言っているのではありません
必要です
将来学校へ戻ってもらうのが前提です
しかし、それまでの間、学習をつくり出しましょう
学校は、行くだけで授業があり主体的能動的に学習に取り組まずとも
カリキュラム任せで学習が進み学年が終わると
一定の学力が付いていることを望むことができます
親も安心ですよね、
通知表やテストなどでどの程度の学力が子ども付いているか
簡単に測ることができるわけです
教科書は無償で提供されるわけですし、様々な学習教材も揃っています
自分でやっていくことが必要になるかも知れません
本屋に行くと、参考書に問題集と揃っています
何なら難関中学校・高校に進学だって可能な勉強ができます
学校では「指示待ち」子どもがたくさん生まれて
自分から主体的に学ばないという課題は、
かなり昔からいわれ続けてきました
そこで現れてきたのが、
子どもの「主体的な学び」「アクテイブラーニング」(←最近このようには呼ばない)
です
子どもが自ら考え課題を解決していく授業、課題解決授業です
課題解決とはいっても、課題は教師が与えて行くことになるのですが
それまでのような講義型の授業では、
OECDのPISA調査では、答えられない学力を問われるようになりました
これらの授業に対応することが(授業づくり)
日本の学校の教師には難しかったのいう側面もあり
なかなか定着していきませんでした
このように、子どもが自ら考え学習課題に取り組み解決していく学習が
学校でも作られるようになってきました
人数の少ない複式学級では、昔から子どもたちが司会を務めなたら、
授業を進めていく形式は取られてきています
私の言いたいのは、学習は自分でできるようにならなければ、
将来必要な生きていく学力にはならないとです
教えられた知識では、自分で思考していないので、それらを使って
再現していくことができないのです
これらを踏まえ、家庭では、勉強への心配に時間を費やさずに
学習内容の学年の終着点は分かっていますので、子どもの興味関心を活かして
3月まで取り組んでいくことで、いいのです
不安や心配をしていないで、
子どもの主体的な学習をつくっていくことをおすすめします
子どものできる範囲から取り組んでくださいね

サロン概要
アクセス
- 所在地
和歌山県御坊市 - 電車でお越しの場合
御坊駅下車 - 営業時間
平日9:00~17:00 / 土日祝定休
090-9621-7137
ご来社の場合はお電話でお問い合わせください