
例えば、学業の遅れがある場合は、基礎的な部分から無理のないペースで学び直しを行う
マンツーマンの学習支援が有効です
また、学校への通学が難しい場合は、
オンライン学習を活用して自宅で学べる環境を整えることも重要です
さらに、学習だけでなく心のケアも必要な場合には、
心理カウンセリングやフリースクールでの交流活動を組み合わせることで、
学びと心の健康を両立させることが可能です
これらの方法を適切に選び組み合わせることで、
子ども一人ひとりに合った支援が提供できます
不登校の原因にはいじめ家庭環境の問題学業へのプレッシャー
精神的な不安などさまざまな要素が絡み合っており
一般的な教育方法だけでは不十分です
本稿では不登校児童の学習における課題現在の支援策そして
効果的な学習方法について具体的に解説します
不登校児童が直面する学習の課題
学習の遅れ
不登校児童は学校に通えない期間が長引くことで授業の進度に遅れが生じます
特に積み上げ型の科目である算数や理科語学では、
基礎が不足することで応用問題の解答に苦労したり、
新しい概念の理解が遅れるといった問題が生じます
例えば算数では、基本的な四則演算や分数計算が未習熟だと、
比例や面積計算のような応用的な問題に直面した際に
理解が進まないことがあります
この結果、算数全体に対して苦手意識が強まり、
次第に学習意欲の低下にもつながる危険性があります
また、理科では、例えば水の沸点や簡単な実験手順といった基礎を理解していない場合、
化学反応やエネルギーの概念などより高度な内容を学ぶ際に
大きな壁に感じることが少なくありません
基本的な実験手順や概念を理解していない場合、高度な問題に進む際に大きなハードルを感じることが多いです さらに語学では、文法の基本や単語の暗記が不足していると文章全体の読解が難しくなるため、苦手意識が増幅しやすくなります
さらに、語学では単語や基本文法の知識が欠けていると、
文章の読解や会話の練習が困難になり、
実際のコミュニケーションに対する不安を強めてしまうことがあります
モチベーションの低下
学校への嫌悪感や自己否定感を抱える不登校児童は学習への意欲を失いやすいです
また、周囲から取り残されているという焦りがさらに
モチベーションを低下させる要因となります
具体的には「自分だけ遅れている」と感じることで無力感が強まり、
次第に学びへの興味を失ってしまうことがあります
このような児童には小さな成功体験を積み重ね、
学習への自信を取り戻す支援が必要です
孤立感とサポート不足
学習を支える環境が整わない場合、不登校児童は孤立感を深めます
特に家庭での学びだけでは十分な支援が得られないことが多く、
学習進度の遅れや学びへの不安が増幅します
例えば親が仕事で忙しく、子ども一人で学習を進めなければならない場合、
分からない部分が解消されないままとなることがあります
これを防ぐため、地域の支援団体やオンラインツールを活用して
多角的なサポートを提供することが重要です
心の健康と学業の両立
精神的な不安やストレスを抱えている児童にとって
無理に学習を進めることは逆効果です
例えば、カウンセリングを並行して受けることで
心理的な安定を図りながら学習支援を行うと、
より良い成果が期待できます
また、音楽やアートセラピーを通じて
気持ちをリフレッシュさせる活動を取り入れるのも効果的です

不登校児童を支える学習環境
フリースクールや適応指導教室
フリースクールや適応指導教室(教育支援センター)は、
不登校児童にとって安心して学べる環境を提供します。
例えば、フリースクールでは子どもの興味や個性を重視した少人数制の授業が行われ、
個別対応が可能です
特定の教科だけでなく、音楽や美術、演劇などの幅広い活動を通じて
学びへの意欲を引き出します
また、適応指導教室では、心理的なサポートやグループ活動を取り入れながら、
学習の遅れを取り戻す機会があります
地域によっては、農業体験やボランティア活動を通じた実践的な学び
を取り入れているところもあり、多様な選択肢が用意されています
これらの施設では他者との交流を促し、社会性や自己肯定感を育むことが可能です
例えば、少人数制の授業では子どもの興味に基づいたテーマで学ぶことができ、
学ぶ楽しさを再発見する機会となります
また、グループワークや体験型学習を通じて
他者とのコミュニケーション能力も育むことが可能です
オンライン教育
近年、インターネットを活用したオンライン学習が広がっています
例えば、動画授業では学年や教科ごとに細かく分けられた教材を視聴でき、
児童が特に苦手な部分に重点を置いて学ぶことが可能です
また、オンライン家庭教師を利用することで、リアルタイムで質問をしたり、
個別の学習計画を立ててもらうことができます
具体的な例として、スタディサプリやオンライン学習プラットフォームClassiを利用すれば、
動画視聴の復習機能や、進捗を確認できる機能が搭載されているため、
学びを効率的に管理できます さらに、教育アプリを活用して、
クイズ形式で楽しく学べる教材を組み合わせることで、
子どもの興味を引き出すことができます
学校との連携
学校が提供する個別支援計画(IEP: Individualized Education Plan)を活用し、
学習内容を調整したり段階的な登校支援を行う体制も整っています
具体例として、学級担任や専門教員と連携して定期的な面談を実施し、
学習目標の進捗を共有することが挙げられます
さらに、家庭と学校をつなぐ連絡帳を活用して、
日々の状況を共有する仕組みを取り入れるとより効果的です
家庭学習のサポート
家庭での学習をサポートする際には親が過度に指導するのではなく、
見守る姿勢が重要です
例えば、親子で一緒に学習アプリを操作したり、
簡単な問題を一緒に解く時間を設けると、
子どもが孤独を感じずに学びを進めることができます
また、子どもが興味を持つテーマの本や教材を選び、
自分のペースで学べる環境を整えることも大切です

不登校児童の勉強方法とポイント
1. 学習目標の設定
児童の状況に応じて短期的かつ具体的な目標を設定します
例えば、1日10分だけ読書する場合、
児童が好きな物語やイラストが多い本を選ぶと良いでしょう
また、数学では1日1問の簡単な計算問題を解く目標を設定することで、
自信をつけながら基礎を固めることができます
さらに、理科に関しては1日1つ身近な自然の観察をするなど、
楽しく学べる目標を取り入れると効果的です
こうした小さな目標を達成することで、
学びへの興味と自信を徐々に高めることが可能になります
読みやすい内容から始めることで、楽しみながら文字に触れる時間を作れます
また、百科事典や図鑑など興味を引くテーマの本を選べば、
知的好奇心を刺激し、学びへの意欲につながります
好きな教科だけを学ぶといった実現可能な目標を掲げることで達成感を得られます
2. 興味を活かした学習
子どもの興味を引き出すことが学びへの第一歩です
例えば科学実験キットを使えば、子どもが自ら手を動かし、
科学の法則や自然の仕組みを楽しく学ぶことができます
また、アートプロジェクトでは絵画やクラフトを通じて創造力を養いながら、
色彩や形状の基礎を学ぶことが可能です
他にも、子どもが好きな漫画を使って
物語の構成やキャラクターの心情を考える活動を取り入れると、
読解力や批判的思考を育む良いきっかけになります
これらを通じて、学びの抵抗感を自然と減らし、
楽しみながら学べる環境を作ることができます
3. 反復と習慣化
短時間の学習を毎日続けることで学びの習慣が形成されます
例えば、毎朝10分間だけ計算問題を解く習慣を作ることで、
少しずつ自信がついていきます
同じ時間に簡単なタスクをこなすことで
継続性を持たせることが重要です
4. 成功体験の積み重ね
小さな成功体験を積み重ねることで児童の自己肯定感が高まります
例えば、簡単な問題を解いた後に親や指導者が「よくできたね」と褒めることが、
次へのモチベーションにつながります
保護者や指導者が褒めるポイントを増やし、
学びの楽しさを感じさせる工夫が必要です
5. 柔軟なスケジュール
児童の生活リズムに合わせて学習時間を調整することも効果的です
例えば、朝が苦手な場合は昼以降に学習を始めるなど
無理のないスケジュールを組みます
さらに、学習とリフレッシュの時間を交互に配置することで、
集中力を持続させる工夫も有効です
6. ソーシャルスキルの向上
学業だけでなく社会性の回復も重要です
オンラインやフリースクールでの同年代との交流が
児童の社会性を育む機会となります
例えば、共同プロジェクトを通じて役割分担を学び、
協力して成果を出す経験が自己肯定感の向上につながります
保護者と周囲の役割
1. 子どもの心を理解する
不登校の背景には学校や友人関係への不安ストレスがあります
まずは子どもの気持ちを理解し、
安心できる環境を整えることが大切です
例えば、日常的に子どもと対話する時間を設けて、
些細なことでも話しやすい雰囲気を作ることが重要です
2. 過度なプレッシャーを避ける
学び直しを急ぐあまりプレッシャーをかけることは
子どもの負担を増やします
焦らず子どものペースを尊重することで、
自然と学びへの意欲が湧くことを目指します
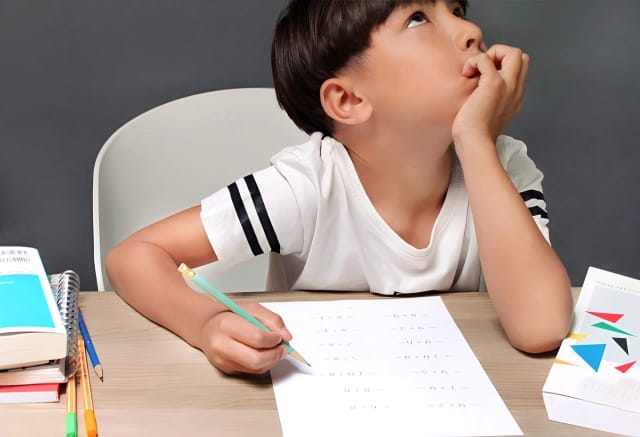
まとめ
不登校を乗り越え、学習への不安や心配を解消するためには、
個別対応と柔軟な支援が必要不可欠です
学業の遅れやモチベーションの低下、孤立感など、
不登校児童が直面する具体的な課題を丁寧に分析し、
適切な学習環境を整えることで、学びへの興味と自信を取り戻す手助けができます
フリースクールやオンライン教育の活用、家庭学習のサポート、学校との連携など、
多様な選択肢が用意されていることを活かして、
それぞれの児童に最適な支援策を見つけることが重要です
また、学びへの取り組みは学業だけにとどまらず、
心のケアや社会性の回復を含む広範な支援が求められます
保護者や周囲の大人が子どもの気持ちに寄り添い、
焦らず子どものペースを尊重する姿勢を持つことで、
子どもが安心して学びを再開できる環境を提供することが可能です
このような包括的なアプローチが、
不登校児童が未来へ向けて新たな一歩を踏み出す力となります
以上是非参考になれば幸いです

メンタルオフィスKaze代表の視点
勉強はやる気になればどこでもできる
これに尽きます
学校に行かなければ、「勉強が遅れる」「勉強が分からなくなる」
このことでの、焦り
学校へ行っても、もう教科書は進んでいて分からないのでは
今日もみんな勉強して進んでいるのでは、そんな思い
「勉強はどこでもやれるといわれても
大変ですよ」
こう思いますよね
正直な気持ちです
しかし時代は進んでいます
様々なネットワークが生まれ、物理的な環境も
子どもの自由な選択肢が広がっています
もちろん、ネット環境が整備されていることも大きいです
私たちがすべて把握していないであろう様々な学習が
インターネットの中にあります
小学生に早いですが、世界中の大学の講義も視聴可能です
かつてインターネットの無い時代では、物理的な移動をしなければ
できなかった学習や体験が可能になっています
しかも、家から仮に出ることができない状態であってもです
活用しない手はありませんよね
YouTubeの中にも多くの授業が存在します
そう考えていくと、学校でなければ勉強ができないという
強迫観念にも似た追い詰められた気持ちが、解き放されて
何とかなるのではないかと考えるのではないかと思います
子どもに、教えてあげなければならないのは、
活用方法であり、勉強の中身ではありません
学校で配られる教科書は、文科省から自治体を通して無償で配られています
あなたがやる気になれば、教えることも可能です
一人で取り組めば、進むのも早いでしょう
もちろん子どもの様子によっても違ってきます
教科書については、学校でどんな勉強がなされているか、
参考にできる羅針盤として使えるでしょう
とりあえず算数と国語でいいのではないでしょうか
教科書の使い方は、
教科書で勉強すること
教科書を通して学校の学習の進度を測ることができること、
だと思います
さて、余裕があれば教科書を使って子どもと学習をしましょう
に加えて
まずあなたにしてほしいことは、
①物理的に可能な学習及び学習体験をつくることです
これは、自分の自宅から行ける行動範囲の中で、どんな学習ができるか
どんな子どもに関係するネットワークがあるかを見つけることです
そして、それぞれを具体的に1か月あるいは1週間で計画をすることです
子どもが不登校で落ち着かない時期には難しい活動かも知れません
このコラムは、どのようにして
子どもの不登校に向き合い
「勉強の不安を解消するか」がテーマです
何もせず、不安は解消できません
あなたが落ちついいて前に向かうことです
子どもがあなたの計画に乗って動いてくれるとも限りません
子どもの様子を見ながら子どもと相談しながら、学習活動をしていきます
自分で教科書を見ていくことができるのであれば、それをしてください
教えればやるなら教えてください
ネットワークの中で、外部団体の活動に参加するなら参加させてください
様々な情報をあなたは探ってください
②次に、インターネット上での学習環境等の構築です
インターネット環境においても、Wi-Fi環境の整備
タブレットやPCの使い方と学習に役に立つコンテンツの獲得など
やることがたくさんあります
大変ですが、学校でないところで学習をさせるためには
学校でないところの学習環境を整えることが必要です
これ、気が重いことかも知れません
軌道に乗っていくまで時間と労力が必要です
自らだけの力では難しいでしょう
だれかに相談することも必要です
誰かとは、知人ということではありません
必ず、不登校関係等で活動している関係者が地域にはいます
ニュートラルに、ある一定の偏りのない情報を収集するために
様々な人の話を聞いてください
情報源が偏ってしまうと私は心配です
なかなか難しいですよね
あなた自身が学校に囚われてしまわないで、
目を広い世界に向けていき、ゆったりと深呼吸をしてください
スポーツでも不安を解消するのは、「練習」だと言われます
頭の中でいくら考えていても不安は雲散霧消することはありません
動いてこそ解消していきます
とりあえず一歩
何か仕事があって、
「やらなあかん」と考えて、なかなかその気にならず、
まだ手つかずの状態というのは誰でもあります
このような仕事でにおいても、ひとつでも取りかかっておくことがコツです
そうすることで不安は解消する方向へ進んでいきます
では、最初の一歩を進めてくださいね
メンタルオフィスKaze
サロン概要
| 名称 | メンタルオフィスKaze |
| 英文社名 | mentalofficekaze |
| 代表 | 奥 明浩 |
| 所在地 | 和歌山県御坊市 |
| TEL | 090-9621-7137 |
| メール | 1z2b3m4w1234@gmail.com |
アクセス
- 所在地
和歌山県御坊市 - 電車でお越しの場合
御坊駅下車 - 営業時間
平日9:00~17:00 / 土日祝定休

